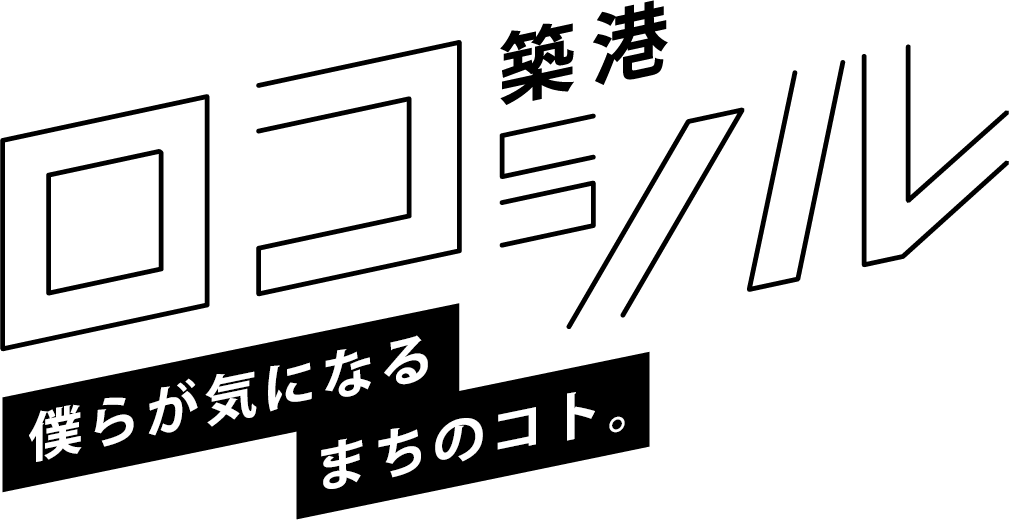おはようございます。
毎日寒いですね。
チコは、もう・・凍りそう・・・
では、早速前回の続きです!
費用はなんとかクリアした天保山の浚渫問題。
次なる問題は、浚渫より出る大量の土砂の処理でした。
この問題を解決したのは、大浚請負人葭屋庄七。
「記念に島を作って、山でもこしらえたらおもろいんちゃいまっかーー(妄想)」
さすが、大坂人!!ノリがいい!

御救大浚えは町々ごとの人が、お揃いの半纏・襦袢・脚絆に身を固め、ノボリを立てた五、六艘づつの船に
分乗し、鉦や太鼓で囃し立て川を漕ぎ下る。砂持たちは速さと土砂の量を競いあったそう。
そして、その様子を見ようと近国からも 見物客が詰めかけ、川辺には腰掛け茶屋や屋台が所狭しと並んだ。
賑わいは、日増しに、大騒ぎ、大浮かれに変わっていき、
川には大坂中の屋台船が停泊したらしい。
川浚えは砂持だけでなく各町からは町人・借家人が、人としてこぞって労働奉仕に赴いた。

こんな感じ??
御加勢に参加した は総勢13万以上にもなったそうである。
当時の大坂の人口が37万人なのでこれは驚異的な数である。
民衆は、仕事もせずに昼間から太鼓や笛を囃し立て、腰には鈴に鳴子をつけて踊り狂ったらしい。
町中の鈴が売れ尽くしたそうである。
何がそんなに楽しいのか浮かれすぎて、私財を使い果たした輩もいるという。
もはや狂気の沙汰としか思えないですね。
でも、ある意味楽しそう!!
いよいよ次回は最終章!
お楽しみに〜